編集注:これは「教会と子ども」の連載第1回目ですが、もともと1つの原稿を2回に分けたものです。ぜひ、後日掲載の第2回目も併せてお読みください。
教会と子ども(1)
教会で子どもたちと関わるとき大切なことは何か?と問われたら「ありのままで愛されていることを伝えたい」とお答えになる方は多いのではないでしょうか。私もそのひとりです。では、どうすれば、教会で子どもたちにありのままで愛されているということを伝えられるのでしょうか。

すわシオンキリスト教会
村上 則之
(祐子夫人とともに)

「ありのまま愛されている」がわからない
私が教会で子どもに関わるご奉仕をさせていただくようになったのは27年前です。しかし、そのはじめの10年くらいの間、私は、教会でよく言われる「ありのまま愛されている」ということが、よくわかっていませんでした。もちろん頭では理解していましたし、十字架の愛を信じていました。子どもたちにも一生懸命それを言葉で伝えていました。しかし、どこか腑に落ちていなかったと思います。ありのままでいい?悪いことをしても?サボってばかりでも?ずっとありのままでいい?キリストの弟子へと成長していくべきでは?
そんな私は、子どもたちを傷つけてしまうことも多く、私のせいで教会に来ることができなくなってしまった子もいました。本当に取返しのつかないことをしてしまい、ずっと申し訳ない気持ちでいます。

子どもたちをわたしのところに来させなさい
苦しんでいた私に、神さまは、ある宣教師の先生と出会わせてくださいました。
私はその先生に「どうやったら、神さまの愛がわかるようになりますか」と質問しました。するとその先生は、
「それは、私は、ビーチを散歩しているときも、夜ベッドに入るときも、ダディ(父なる神)と何でもお話しているんだよ。」
とおっしゃいました。私は、
「よくわかりません。どういうことですか、教えてください。」
とさらに質問しました。

そのとき教えていただいたことが、今では私にとって、教会での子どもの関わり方の原点・中核となっています。
「ムラ、『子どもたちをわたしのところに来させなさい。止めてはいけません』(マルコの福音書10章14節)というみことばを知っているだろう?これは、何歳の子どもまでのことを言っているんだろうね?私は、おとなの心の中にも、幼な子のような気持ちがあると思うんだ。例えば「つらいよー」とか「ムカつく!」とか。そんな、私たちの内にある「子どもの心」も、『わたしのところに来させなさい』と神さまは言っていると、私は思うんだ。だから私は、私の『内なる子どもの声』を、いつもダディ、天の父にお話ししているんだよ。『止めてはいけません』と言われているとおりにね。あるがままの気持ちをお話しするんだよ。でも、私たちおとなはそれを止めてしまう。特にムラ、あなたのような優等生クリスチャンはね。だけど、あるがままの気持ちを神さまに見せないでいたら、あるがままで愛されていることはわからないんじゃないかな。」
先生はこれを「Heart to Heart (心と心の)コミュニケーション」という名で呼んでおられました。

内なる子どもの声
聖書の釈義としては、このみことばが本当にそれを意味しているかなあ?と疑問を感じました。しかし同時に、ありのまま愛されていることを知りたいのなら、まず、ありのままの自分を神さまに見てもらうことが必要だ、というのは納得しました。
また、私の内に、子どものような気持ちがあることも、納得しました。内なる子どもの声…私の中で幼い3~4歳の「のんちゃん」(私の幼少期の呼び名)が、まだ叫んでいるかもしれないと思いました。天の父はその子どもを指して「その子をわたしのところに来させなさい」と招いてくださっているかもしれない…と思いました。
この箇所で、無邪気な子どもたちがイエスさまに近づこうとするのを邪魔したのは弟子たちでした。信仰者である彼らには、イエスさまに近づくには「こうであるべき」のような考えがあったと思います。当時の私も、同じ「べき」を持っていました。しかし、イエスさまは、信仰的でなくても、ワガママなようでも、「子どもたちをわたしのところに来させなさい。邪魔してはいけません」と言ってくれている。私も、あるがままの気持ちを神さまにお話ししてみたい!自分がありのまま愛されていることを知りたい!そう感じました。

天の父に「あるがままの気持ち」をお話しする
それからしばらくして、ある日、私は教会の中高生を引率してスキー場に行っていました。そのとき、私はポケットに入れておいたはずの1万円札が無いことに気がつきました。教会から預かった大切なお金です。私は、中高生たちを他の人に任せて、真っ白なゲレンデを、ひとりで歩き回って探しました。雪がたくさん降っていて、早く見つけないと、お金が雪に埋もれていきます。なかなか見つからず、気持ちは焦りと後悔でいっぱいになってきました。ほとほと疲れ果てたとき、あの宣教師の教えを思い出しました。
「パパ、疲れたよー」
私は、子どものように、あるがままの気持ちを天の父にお話ししてみました。
「何でボクだけこんなことしなきゃいけないんだ!みじめだよー。もうイヤだ!帰りたい!」
そのとき、『そうだよね、そうだよね。そりゃ、イヤになるよね。帰りたくもなって当然だよ』と父が優しく応えてくれた気がしました。

結局、お金は見つかりませんでしたが、父が私の気持ちに共感してくれたことで、愛を感じ、安心と嬉しさが混じったような、とても満たされた気持ちになりました。それまで「主よ、見つかるようにしてください」というのだけがお祈りだと思っていましたが、天の父にあるがままの気持ちをお話しする『心と心のコミュニケーション』のお祈りがわかったような気がしました。
それから、私は、どんなことでも、生活の局面局面で、天のパパにお話しするようになりました。「ボクはこんなに頑張ってるのに、何で教会のみんなはわかってくれないんだよーー」「(牧師の集まりで)居心地悪っるぅ…」「(ベッドに入るとき)あー布団って最高!」。
これらの内なる子どもの声は、本当に、あるがままの私そのものです。
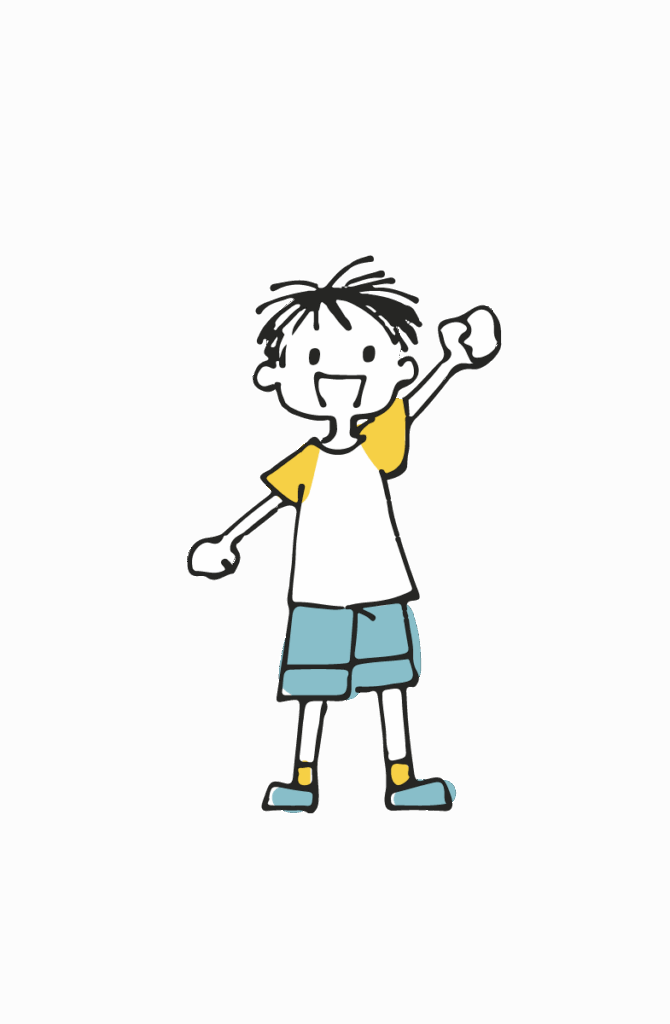
天のお父さんは24時間いつでもどこでも、私がお話しすると、幼い「のんちゃん」の目線までしゃがんで「そうだよね、わかるよ」と言って聴いてくれました。そして「あなたはわたしの愛する子。わたしはあなたを喜んでいるよ(マルコの福音書1章11節より)」「そんなあなたが、わたしの目には高価で尊いんだよ(イザヤ書43章4節より)」と言葉をかけたり、抱きしめたりしてくれました。あるがままの私、どんなにワガママで、自己中心で、イジケ虫な気持ちをお話ししても、いつでも、何度でも、受け止めてくれました。
そのような天の父との心と心のコミュニケーションが楽しくなり、1年くらい続いた頃には、私は「ありのまま愛されている」ことがわかるようになっていたと思います。
それから10年以上経った今「私はありのままで天の父に愛されている息子です!!」というアイデンティティが私の中で深く根を張っているのを感じます(相変わらずイジケ虫で、落ち込みやすいですが、そのままで愛されている子どもです笑)。
子どもたちの「あるがままの気持ち」を聴く
そのようにして、私は、教会で子どもたちと関わるとき、あるがままの気持ちを聴くということを大切にするようになりました。私は天のパパにあるがままの気持ちを受け止めてもらうことで、ありのまま愛されていることがわかりました。ですから、私も、子どもたちにありのまま愛されていることを伝えるためには、あるがままの気持ちを充分に聴くことが大切だと思うようになりました。父が私を愛してくださったように、子どもたちを愛したいと思いました(ヨハネの福音書15章9節より)。
気持ちを共感・肯定してもらえると安心する
子どもたちは、おとなにありのままの気持ちを充分にきいてもらえると安心するようです。教会で、子どもたちが遊んでいると、トラブルが起こります。泣き出す子も、怒りだす子もいます。そんなとき、とにかく、その子のそばに寄り添ってあるがままの気持ちを聴く。そして、そのままを共感・肯定する言葉を伝える。
―― そうなんだね、悲しかったね。そうだよね、つらかったね。
一緒になってその気持ちを感じ、一緒にはらわたを震わす(聖書で「あわれむ」と訳されている語は、内臓が揺さぶられるほどの強い感情をともなう愛と共感を表すそうです)。
それだけで、子どもたちが安心するのを、私は今まで何度も経験しました。不思議です。さっきまでケンカしていたのに、けろっとしてまた一緒に遊び始めたりします。私たちは、「大丈夫!大丈夫!」「痛くない、痛くない」と励ましたり慰めたりしないといけないと思ってしまいますが、とにかく、気持ちをそのまま聴いてあげるだけで、子どもたちは安心するようです。

「気持ち」を話すことに慣れていない

私たちは普段、いろんな会話をしていますが、自分の気持ちを言葉にして相手に伝えたり、相手の気持ちを聴いたりすることに慣れていないように思います。
ですから、子どもたちも、何か問題が起こったとき、いきなり「今どんな気持ち?話して!」と言っても、なかなか話すことが難しいようです。気持ちを聴こうとして、返って嫌がられてしまったことも何度かあります。普段、一緒にアイスクリームを食べたり、公園に連れて行ってあげるなど、他愛ないおしゃべりから、ある程度の関係を築くことは必要のようです。
それから少しずつ、子どもたちの日常生活でも「気持ち」を聴く会話を心がけます。たとえば、もうすぐ運動会という話題だとすると、5W1Hを用いて、まずは、いつあるの?何の競技に出るの?だれと競争するの?などの会話をし、次第に、なぜその競技が好き/嫌い(という気持ち)なの?スタート前はどんな気持ち?負けたときどんな気持ち?などお話しすると、お互いに気持ちをやりとりする練習になると思います。
それがどんな気持ち「赦せない」「やり返したい」のようなものであっても共感的に傾聴する(同意・同調するのではなく「あなたはそう感じたんだね」と相手の気持ちをそのまま肯定しながら聴く)ことが大切なんだ、と学ばされています。
(怒りの感情の場合は、それは第二感情ですので、いくら共感しても落ち着かないことも多いです。ひとまず肯定することも必要ですが、その奥にある第一感情に注目し、たとえば「傷つけられてみじめな気持ち」「拒絶された恐れ」など、を聴き出せるように「どうしてそんなに腹が立つんだと思う?」など質問できると良いと思います)
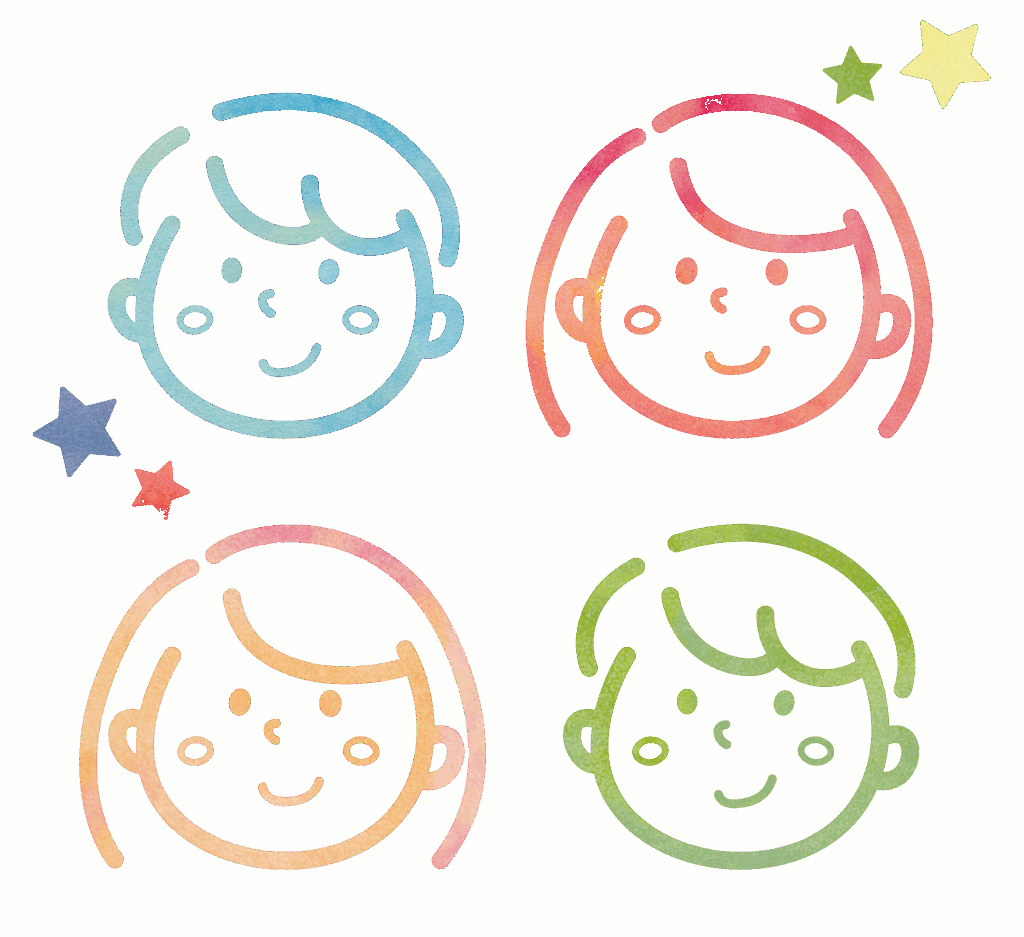
まずおとなが、天の父との関係の中にいること

子どもとの関わり方というとき、SNSなどには「子どもが言うことをきくようになる魔法の言葉」のようなものを見かけますが、私は何か、子どもをおとな(教会)の思いどおりにコントロールしようとしているようで、あまり好みではありません。同様に、「あるがままの気持ちを聴く」ということも、子どもとの関わり方のHow to(方法論)のようにとらえないようにしたいと思います。
大事なことは、生きた関係―私たちおとなが天の父との親しい交わりの中にいることだと思います。私自身が、あるがままの気持ち(内なる子どもの声)をパパに聴いてもらえるってこんなにウレシイ!安心!と生きた体験をしていること。私は天の父に愛されている息子(娘)!と感じられていること。父なる神とのリアルな交わりの中にいることを、大切にしたいと願っています。
逆から言うと、私が父との親しい交わりの中にいれば、自然とそれが子どもたちとの関わりに現れてきます。本来の私はすぐ「コラ!」「ダメ!」とか言ってしまうタイプなのですが、最近はなぜか「そうか、そうか」「そうだよねー」と子どもたちの気持ちに共感する言葉が口をついて出て来ることに自分で驚くことがあります。父が私を愛してくださったように、子どもたちを愛する。天の父と私との関わり方から、私と子どもたちとの関わり方が溢れ出て来るものでありたいです。

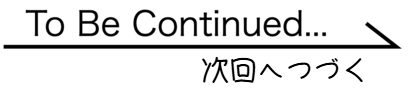

a-300x169.jpg)
感想・コメントはこちらに♪