編集注:これは「教会と子ども」の連載第2回目ですが、もともと1つの原稿を2回に分けたものです。第1回目をまだ読まれていない方はぜひ、そちらも併せてお読みください。
教会と子ども(2)

すわシオンキリスト教会
村上 則之
(祐子夫人とともに)
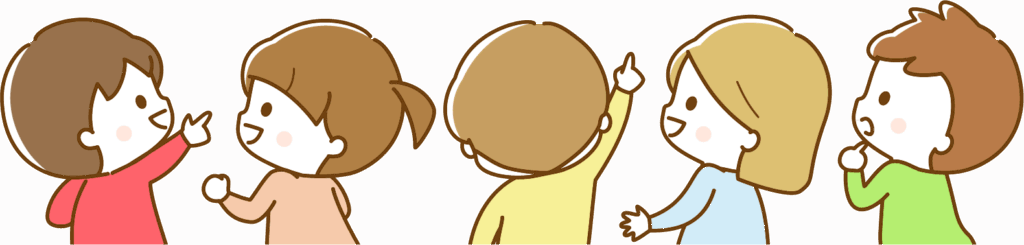
子育て経験がなくても
私たちの教会で、子どもに関わる奉仕をしてくださっているチームの中には、中高大学生や独身の社会人がいます。彼・彼女らは子育てをした経験がありません。しかし「あるがままの気持ちを天のお父さんにお話しする」という神との親しい交わりを体験しているので、教会の子どもたちにも同じように接してくれています。それはとてもうるわしい姿で、いつも感動しています。
また、自分が子どもの頃、親にあまり関わってもらった経験がないので、子どもとどう接していいのかわからない、とおっしゃる方々も多いかもしれません。私も子どものときは教会に通っていませんでしたし、肉の父親とは良い関係だったとは言えません。ですから、教会での子どもとの関わり方が間違っていたことがあったと思います。

いずれにしても、人間(肉)の親、教会のおとなも、私も、みんな不完全です。だからこそ、完全な愛の父が必要なのだと思います。私たちが天の父に愛されている子どもになって、あるがままの気持ちを聴いてもらえる親しい交わりの中で喜んでいることこそが、教会で子どもたちと関わることにおいて最優先されることだと感じます。
おとなも「子ども」になる
立派なCS教師になろう、子どもたちと関わるためにふさわしいおとなになる「べき」、と頑張ってしまう前に、「赤ちゃん返り」のようにして、幼な子のように父に甘えるところから始めるほうが、私たちは健全に成長できるかもしれません。
私は、みことばと祈りで自分の感情を乗り越えることこそ強い信仰だ、ととらえていたところがあったと思います。受験、仕事やスポーツで「つらい」「いやだ」「キライ」などと言っていないで、そういう弱い感情に勝たないとダメだと学んだのだと思います。感情とは、何か弱いもの・劣ったものだと考えていました。25歳でクリスチャンになって人生は変えられたものの、そのような考えを、そのまま信仰に当てはめしまっていたと、今になって気づきます。
しかし、自分のあるがままの気持ち(感情)をないがしろにしては、クリスチャンは返って成長できないと思います。感情に打ち勝つというより、それをそのまま天の父にお話しすることで、私は強く(弱いままで強く)生きられるようになったと感じています。

子とする御霊

私が天の父をパパと呼べる、親しい交わりを体験できるようにしてくださったのは聖霊さまです。「子とする御霊」が助けてくださるので「私は天の父に愛されている子どもなんだ!」と確信することができました。「子とする御霊」は心と心のコミュニケーションをする中でパパとの親しい交わりを導いてくださいます。聖霊が、私たちと父なる神の仲介をしてくださいます。
奴隷・雇人ではなく
私たちは、能力主義・競争社会の中で生きています。魚が水の中で生きていることを魚たちは疑わないのと同じように、私たちは、能力で人の価値を決められることが当たり前の世界に生きています。能力で競い、持ち物で比べ、優越感と劣等感の狭間に住んでいます。奴隷なら、能力が無ければ捨てられることもあるでしょう。しかし私たちは神の子どもです。なのに、こんな能力主義・競争社会にどっぷりつかっているので、ありのまま愛されているなんていう言葉が、子どもたちの心にも届かなくなってしまっていると思います。「子とする御霊」によるのでなければ、私たちは、あるがままで天の父に愛されている息子・娘としてのアイデンティティを確かにすることができません。

放蕩息子のたとえ(ルカの福音書15章11~32節)を思い出します。弟息子は、父のもとに帰るとき「雇人のひとりにしてください」と言うつもりでした。頑張れば、能力があれば、せいぜい雇人としてなら認めてもらえるのではないか…しかし、もう息子と呼ばれる資格はない…と考えたのでしょう。まさに、能力が無ければ捨てられる奴隷(雇人)の霊です。このような考えは、競争社会の中で、私の中にも染みついています。
しかし、父は、弟息子をかわいそうに思い(内臓が震えるほど同情)、あるがままの姿で抱きしめました。服・指輪・履物によって、奴隷・雇人ではなく、息子として回復させました。そして、祝宴で喜び、親しい交わりをしました。
一方、兄息子は、父の家にいながらも、自分は能力があるから愛されている、父のいうことをきく良い子だから息子と呼ばれる資格がある…、と考えていたようです。まるで、教会に通っていながらも、ありのまま愛されていることがわかっていなかった私のようです。私たちは雇人の霊ではなく、子とする御霊によって、父なる神の息子・娘として回復されます。
他のだれとも違う「あなた」
私たちは能力があるから価値があるのではありません。神が造られたというだけで、高価で尊い価値があります。子どもたちひとりひとりは、世界で唯一、だれとも違う、神の作品です。チョー特別な作品です!能力が同じくらいの人はいるでしょう。ひょっとしたら、見た目がそっくりな人もいるかもしれません。しかし、あるがままの気持ち、内なる子どもの声はみんな違います。学校でたくさんの児童が、同じプログラムで動き、同じものを見たり、食べたりしても、感じることはみんな違います。それを感じているのが「あなた」、世界でたったひとり、誰とも違う、唯一の「あなたらしさ」です。内なる子どもの声を大切にすることは、神さまに造られた「あなたらしさ」を大切にすることです。

それなのに、私たちは「みんなと同じようにできる」のが良いことのように考えてしまいます。せっかく他の人と違うように造られたのに、内なる子どもの声を消して、他の人と同じようにしようとしてしまいます。日本人は特にそういう面が強いと思われます。
子どもたちを取り巻く環境は、とても厳しいです。みんなと同じようにできないと、攻撃されてしまう。みんなと同じように感じないと、おかしいと思われてしまう。そういうプレッシャーの中にいる子も多いと思います。ですから教会では、子どもたちの「あなたらしさ」を大切にしたいと願います。それは、あるがままの気持ち、内なる子どもの声に耳を傾けることだと考えます。それこそ、神さまに特別にデザインされた、あるがままの子どもたちひとりひとりの「あなたらしさ」を大切にすることだと思います。

教会は安全基地に
教会は子どもたちにとって、安全基地でありたいと願います、あるがままの自分をさらけ出しても攻撃される恐怖のない、安全・安心な場所でありたいと思います。現代の子どもたちは、すぐに矢が飛んでくるようなあからさまな攻撃だけでなく、罠・疫病・夜襲のように見えないところで忍び寄る攻撃に、いつも息を殺して生活しているかもしれません。自分らしくいることより、他の人に合わせて、内なる子どもの声を止めていると思います。避け所・御翼の陰・砦・大盾は敵の攻撃から身を守るものです。教会は、そのような場所でありたいと願っています。教会では、ありのままの自分をさらけ出しても、バカにされたり、責められたり、否定されたりしない。他の誰とも違う、自分らしい気持ちを堂々と言うことができ、大切にしてもらえる場所になりたいと願っています。
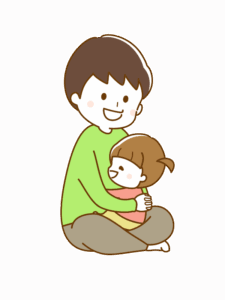
子どもたちは学校に安心・安全を感じられなければ行けなくなってしまいます。教会も、安全・安心を感じられなければ「今週も教会に行きたい」とは思わないでしょう。逆に、教会が、安全基地であれば、みんな大好きになると思います。

教会の子どもたちひとりひとりに、好き・キライ・うれしい・さびしい・楽しい・居心地悪い・みじめ・腹が立つなど、それぞれ気持ちがあります。キャンプが苦手な子、礼拝のゲームが苦手な子、賛美が苦手な子、もいます(たとえ牧師の子どもでも、です)。それは信仰が足りないのではなく「あなたらしさ」かもしれません。ひとりひとりの気持ちをよく聴いて、受け止めてあげたいと思います。
指導はどうするのか?
私がこのようなお話しをすると、よく「気持ちを聴くだけでよいのでしょうか。指導が必要なこともあるのではないでしょうか。」と疑問の声をいただくことがあります。もちろん、教会では正しいことを教えることも、大切な役割です。励ましの言葉をかけたり、アドバイスをしたくなるのも愛だと思います。
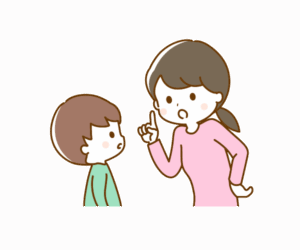
しかし、子どもたちがせっかく、あるがままの気持ちを話したと思ったらすぐに、おとなから「正しいこと」を指導されたら、どうでしょうか。自分の気持ちをおとなに正直に話したら、すぐ正論やアドバイスの矢が飛んでくる。それで子どもたちは、安心・安全を感じられるでしょうか。
まずぜんぶ聴いて受け止める。気持ちを肯定し・共感する。それも、おとな側が「この子の気持ちはわかった!」と思ったところまででは足りないようです。子ども側が「あぁ、この人(おとな)は、私の気持ちぜんぶわかってくれた!!」と充分に安心を感じるまで、ちゃんと聴く。同じ気持ちにまで降りていく。
子ども側が「充分わかってくれた」と感じたら、その後で、おとなである私の気持ちを子どもに伝える。
正直、面倒です…?とても時間がかかります。しかし、ありのままで愛されているということを伝えるには、犠牲が必要なのだと学ばされています。私も、すぐに正しいことを教えたくなります。そもそも、子どもたちの考えていることなんて、聴く前からだいたいわかっているのですから!聴いている時間が面倒に感じ、すぐ指導したくなります。
しかし、イエスさまは私たちの罪に対して、正義を振りかざすのではなく、天から降りてきて、黙って十字架に進み、命を犠牲にしてくださいました。それによって私たちに愛がわかりました(ヨハネの手紙第一3章16節より)。ですから、私たちも、黙って子どもたちのために命を犠牲にすることで(生きている時間≒命)、子どもたちに愛が伝わることを祈ります。子どもたちの気持ちまで降りて行って、話をよく聴く。
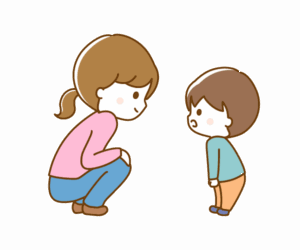
これを続けていると、教会の子どもたちが、こちらがビックリするぐらい、心の距離を縮めて来て、信頼して何でも話し合える関係になっていることや、彼らがまたその次の世代の、自分より年少の子どもたちに同じように関わるように成長している姿に、気がつくことがあります。
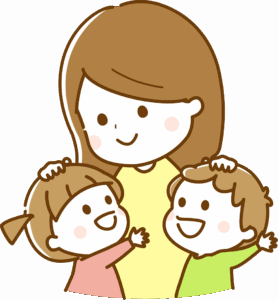


感想・コメントはこちらに♪