「聖書は最高の終活本」

小田島幹彦
大宮キリスト教会
「主の聖徒たちの死は 主の目に尊い。」詩篇116篇15節
終活ブームが続いています。その背景には高齢化、少子化、核家族化があり、死と向き合ったとき助けてくれる人、教えてくれる人がいないという現実があります。「より良い人生の最期」を迎えるためにどのように備えたらよいのでしょうか。今回はクリスチャンの終活について考えてみたいと思います。
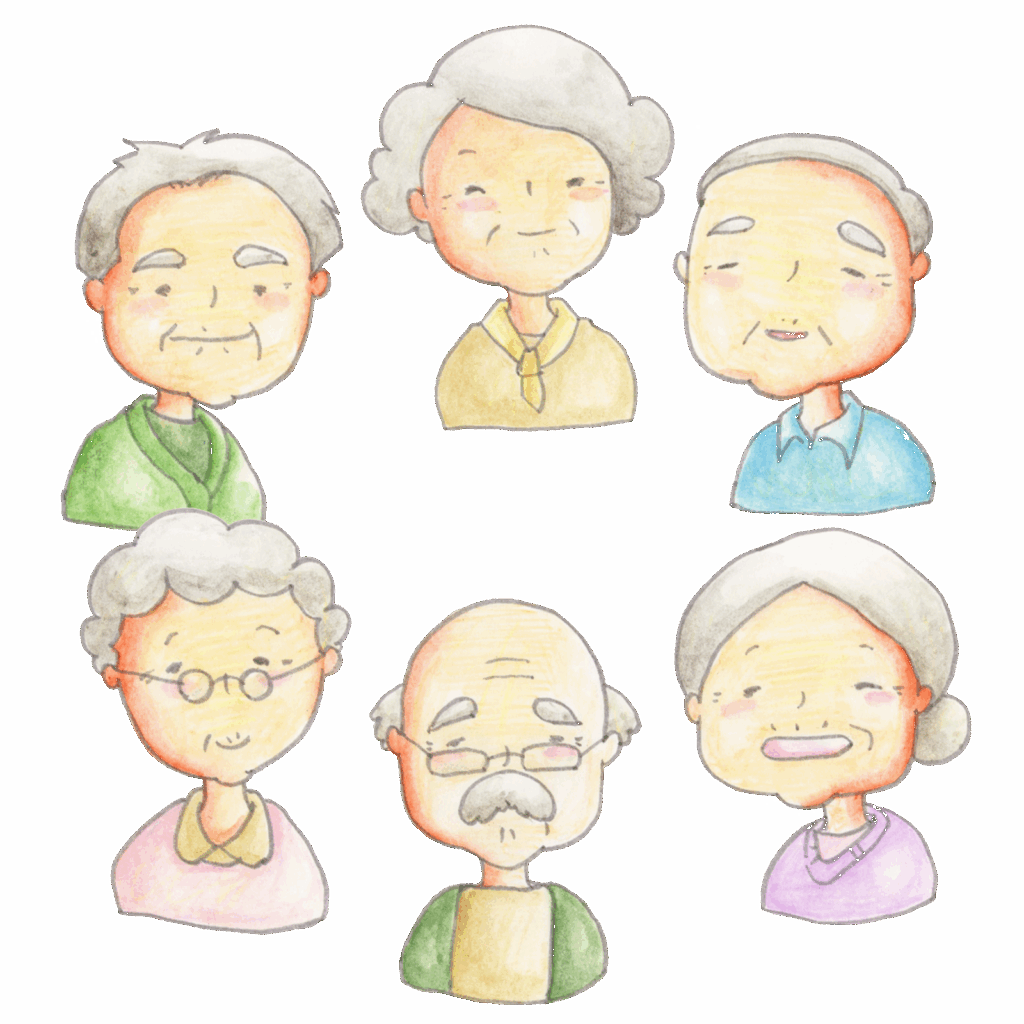
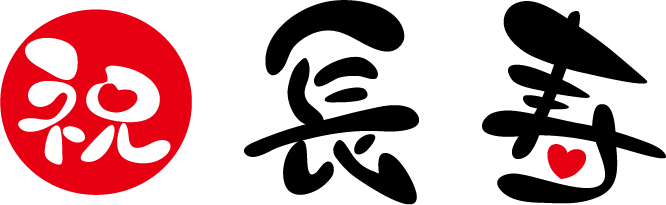
1 終活とは
終活とは死に対する準備活動です。一般的には死後、家族や関係者に不必要な負担や迷惑をかけないように遺品や遺産の整理をすること、トラブルを防ぐために遺言書やエンディングノートを作成することです。スウェーデンに「死の御片付け」と呼ばれる考え方があります。断捨離と内容が重なりますが、年を重ねたら「モノ」を増やさず、不要な物を処分し、遺品整理を楽にしようとする考えです。クリスチャンの終活はもう少し違った目的も含まれます。それは信仰の証と信仰継承の機会とすることです。

終活には以下のことが含まれます。
① 身の回りの整理・整頓、遺品・遺産の整理と処分
② 医療・介護、延命治療などの希望を伝えること
③ 葬儀について、墓について希望を伝えること
④ 遺言書、エンディングノートの作成
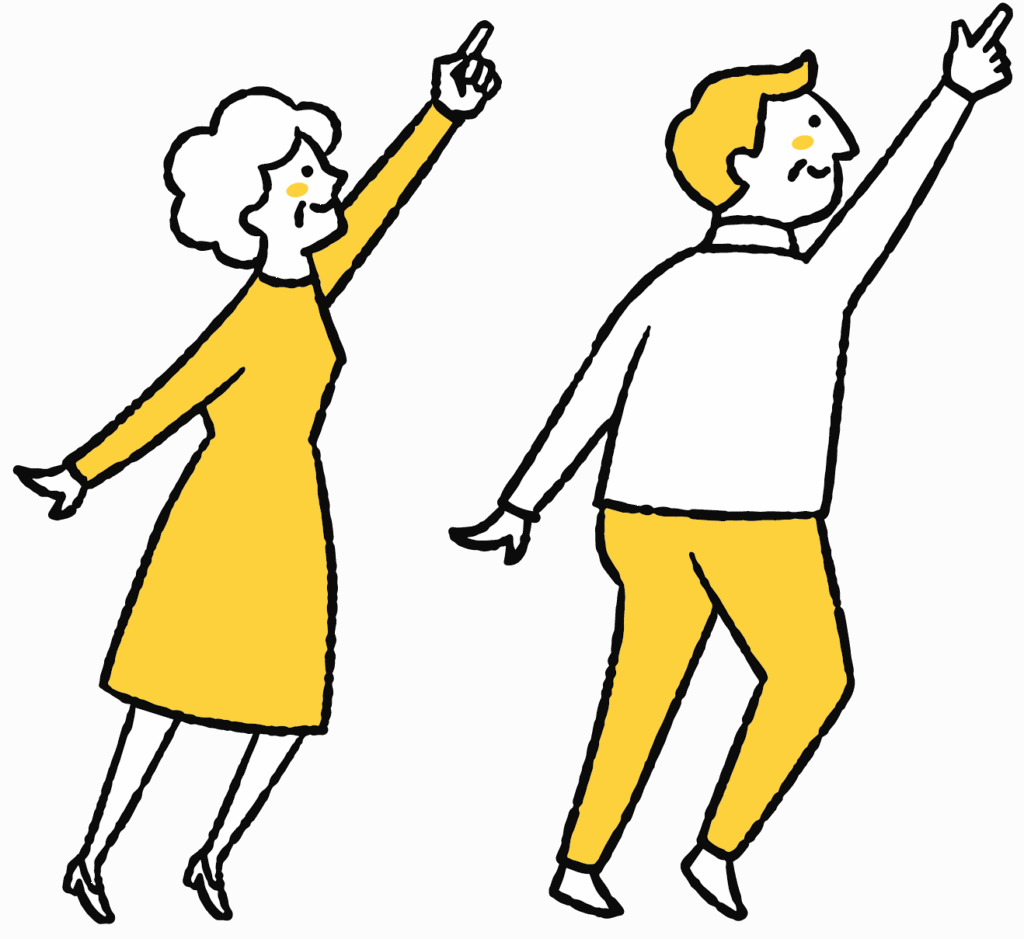
エンディングノートは終活に必要な項目について記載できるようになっており、遺言書的な役割を果たします。エンディングノートや遺言書を残すことは法的な意味合いより、家族や関係者が死後の対応について本人の意志を尊重して行うための意味合いがあります。時間の経過とともに本人の考え方も変わることから最新のものに更新すること、一人ではなかなか書き込むのが難しいのでグループで、または教会の活動の一環としてその機会をもつことなどの工夫が必要でしょう。家族がノンクリスチャンの場合は特に配慮が必要です。エンディングノートを書く理由を伝え、事前に話し合う機会をもちましょう。また独り身の方は教会に申し出て、資料等を預かってもらう必要があるかもしれません。
2.聖書に見る終活
聖書は最高の終活本です。聖書には登場する信仰者の誕生から死に至るまでの歩み、信仰継承、死と葬り、死後の約束などが時にはドラマチックに、時には淡々と描かれます。ユダヤ人は必ず葬りと墓についての遺言を残すと言われています。
ユダヤ人の先祖アブラハムは神に示されたカナンの地に入りましたが、その後の生涯は寄留者として旅人としての生活でした。彼が目指していたのは地上の都ではなく、永遠の都でした(へブル人への手紙11章8~10節)。アブラハムが地上で得た最初の土地はマクペラの洞窟であり、そこに妻のサラを葬り、アブラハムもそこに葬られました(創世記25章7~10節)。この墓地にやがてイサクもヤコブも葬られることになります。ヤコブは臨終にあたり12人の子どもたちを呼び寄せ、一人一人にアドバイスを与えて祝福を祈りました(創世記49章29~33節)。これらの出来事は終活の大切さを物語っています。
主イエスも死に際し、マリヤとヨハネが悲しみに打ちひしがれないように互いに助け合うように配慮されました(ヨハネの福音書19章26,27節)。アリマタヤのヨセフは墓を準備していましたが、はからずも主イエスのご遺体を納めることとなりました。ニコデモは没薬を準備し、アリマタヤのヨセフと共に丁重に墓に葬りました(ヨハネの福音書19章38~42節)。神はその一連の行為を用いて主イエスを三日目によみがえらせ、墓を栄光の場所へと変えられました。
使徒とされたパウロは死に至るまで使命に忠実に生き、その歩みを通して信仰の証を残しました。彼にとっての終活は福音宣教の任務に従うことであり、殉教に備えることでした。死の直前に書き送った手紙で彼はこう言っています。「私が世を去るときが来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。」(テモテへの手紙第二4章6~8節)
聖書は、死という危機に際しても共にいてくださる主に信頼し、その先にある希望に目を留め、勇敢に生き抜いた信仰者たちの姿を数多く描いています。
3.残された人生をよりよく生きるために
クリスチャンの終活は人生のゴール(完成)に向かう恵みのわざです。終活というと悲観的なイメージを持つかもしれませんが、本来の終活は残された人生をよりよく生きるため、一日一日を大切に生きるための活動です。高齢者だけでなく若い人もわざわいの日が来ないうちに死に備える必要があります(伝道者の書12章1節)。クリスチャンの終活は自分の人生を振り返るときであり、信仰者たちの終活に学ぶときであり、主の良くしてくださったことを感謝するときです(詩篇103篇1~3節)。
私事ですが、60歳から70歳までに腎臓がんと前立腺がんを患いました。病気と向き合うなかで死を自分事として意識しました。人生には終わりがあること、その時に備える必要があることを今まで以上に自覚するようになりました。
召される時が近づいたら「ありがとう」と共に「幸せな人生だった」という言葉を残したいものです。召されていく者を見守る者たちは十分なことをしてあげられなかったという責めを感じるからです。この最後の一言によってどれほど慰められるでしょう。召される時がきたら、たとえ涙の谷を通るとしても天に国籍があること、愛する主のみもとに召されること、再会の望みがあることを覚え、涙をぬぐってくださる主にすべてをお委ねいたしましょう(詩篇23篇4節)。
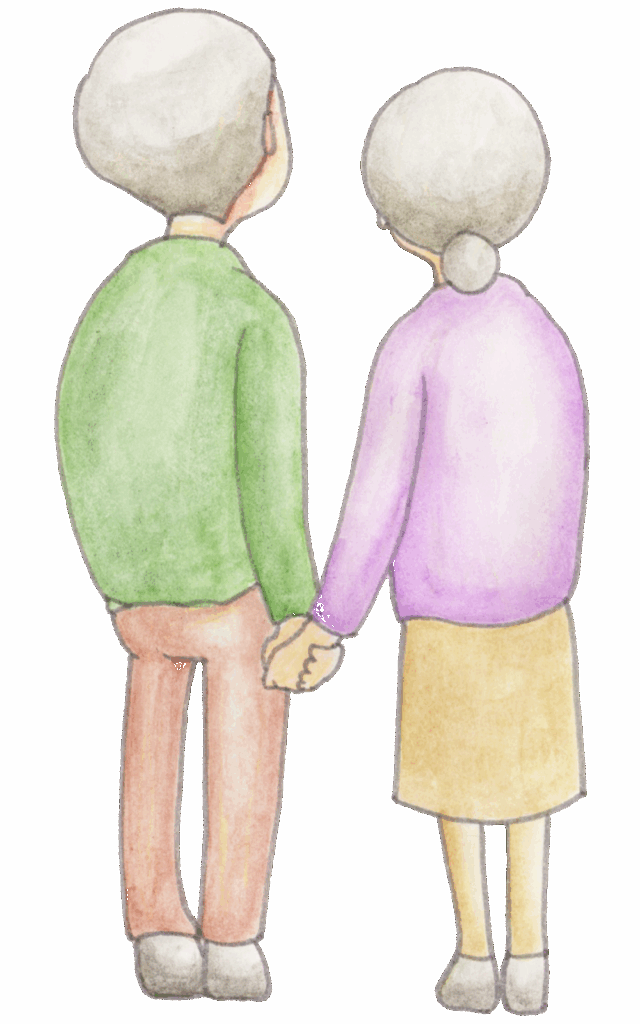

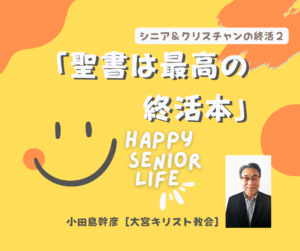
感想・コメントはこちらに♪